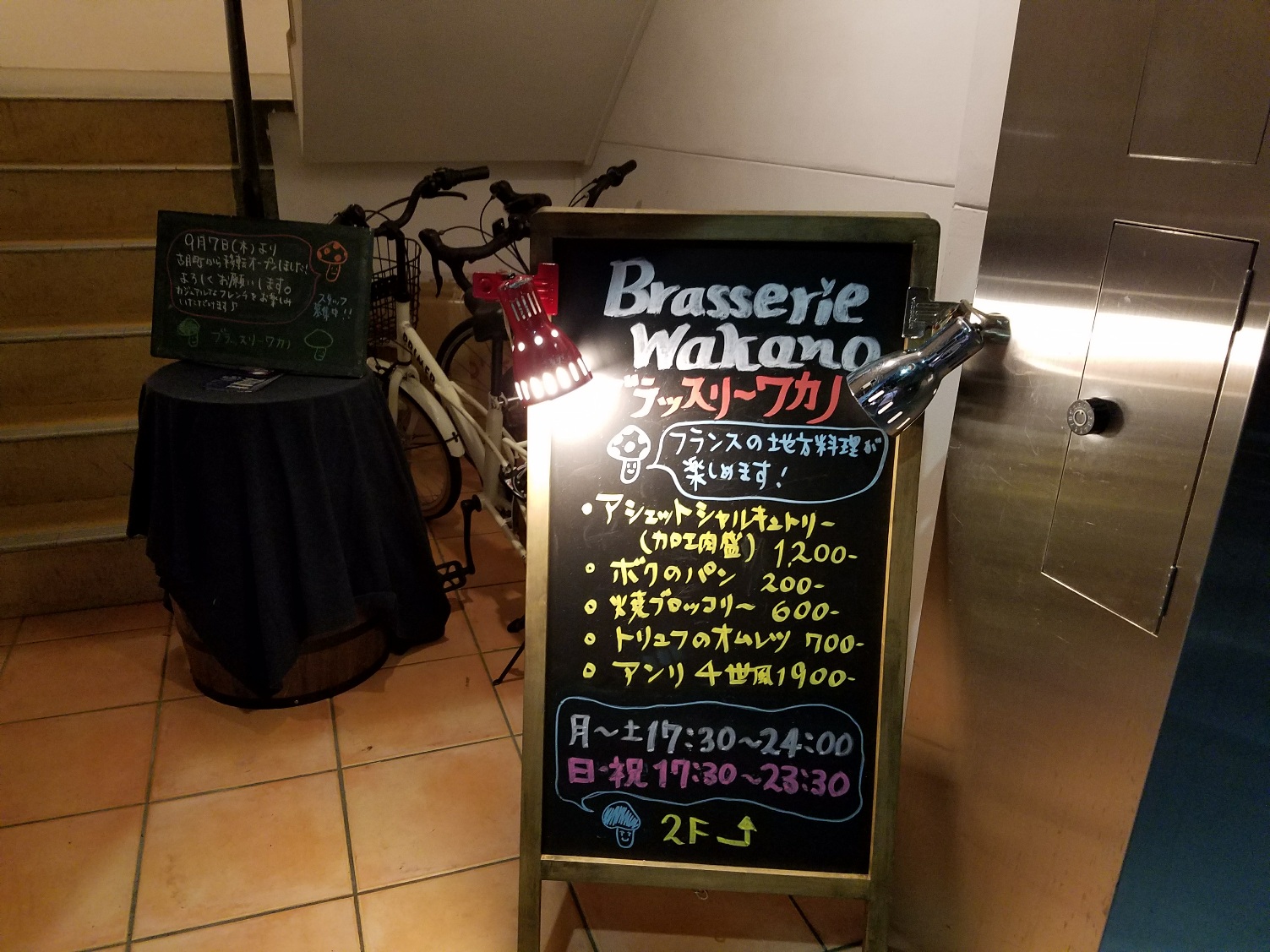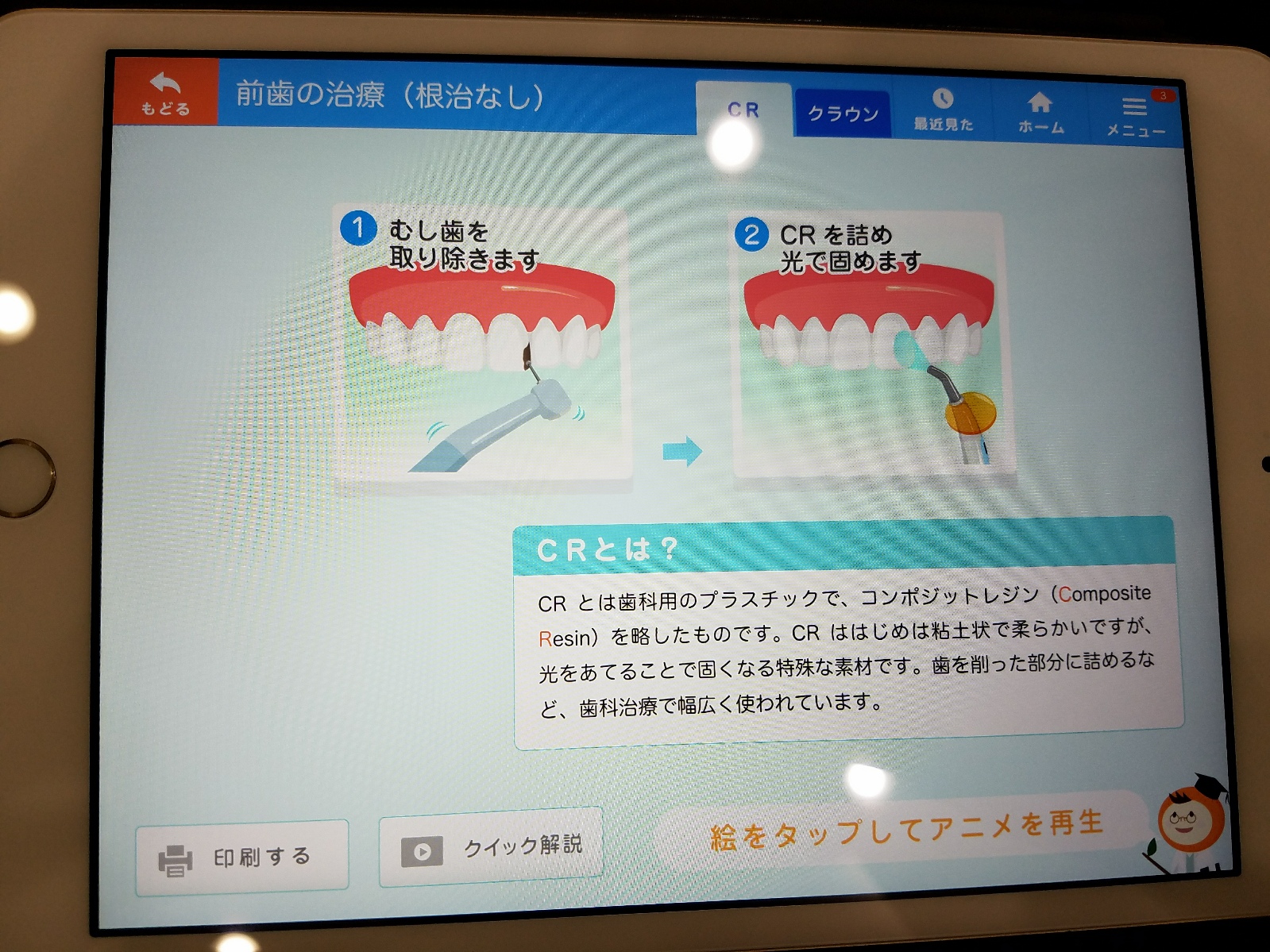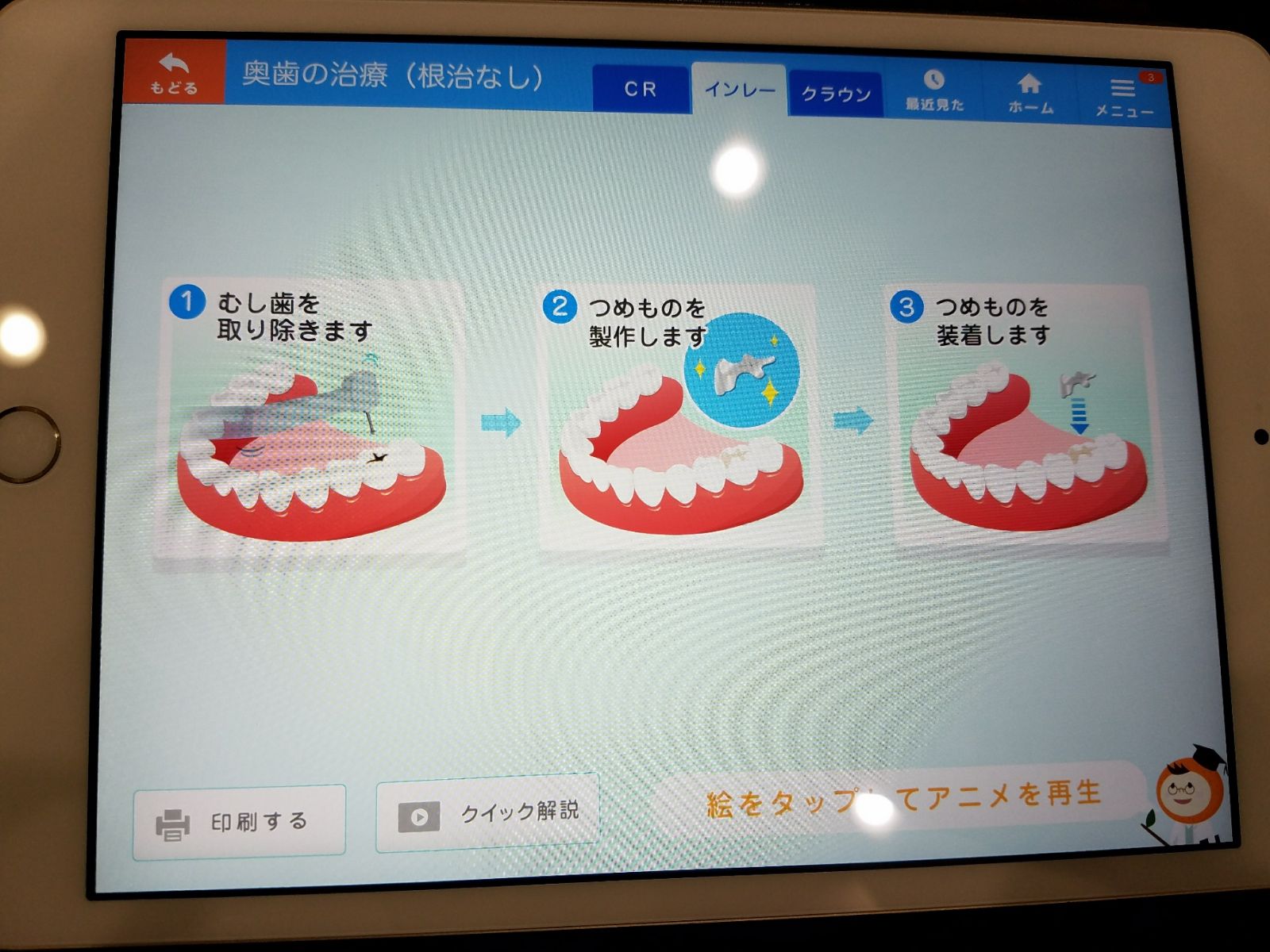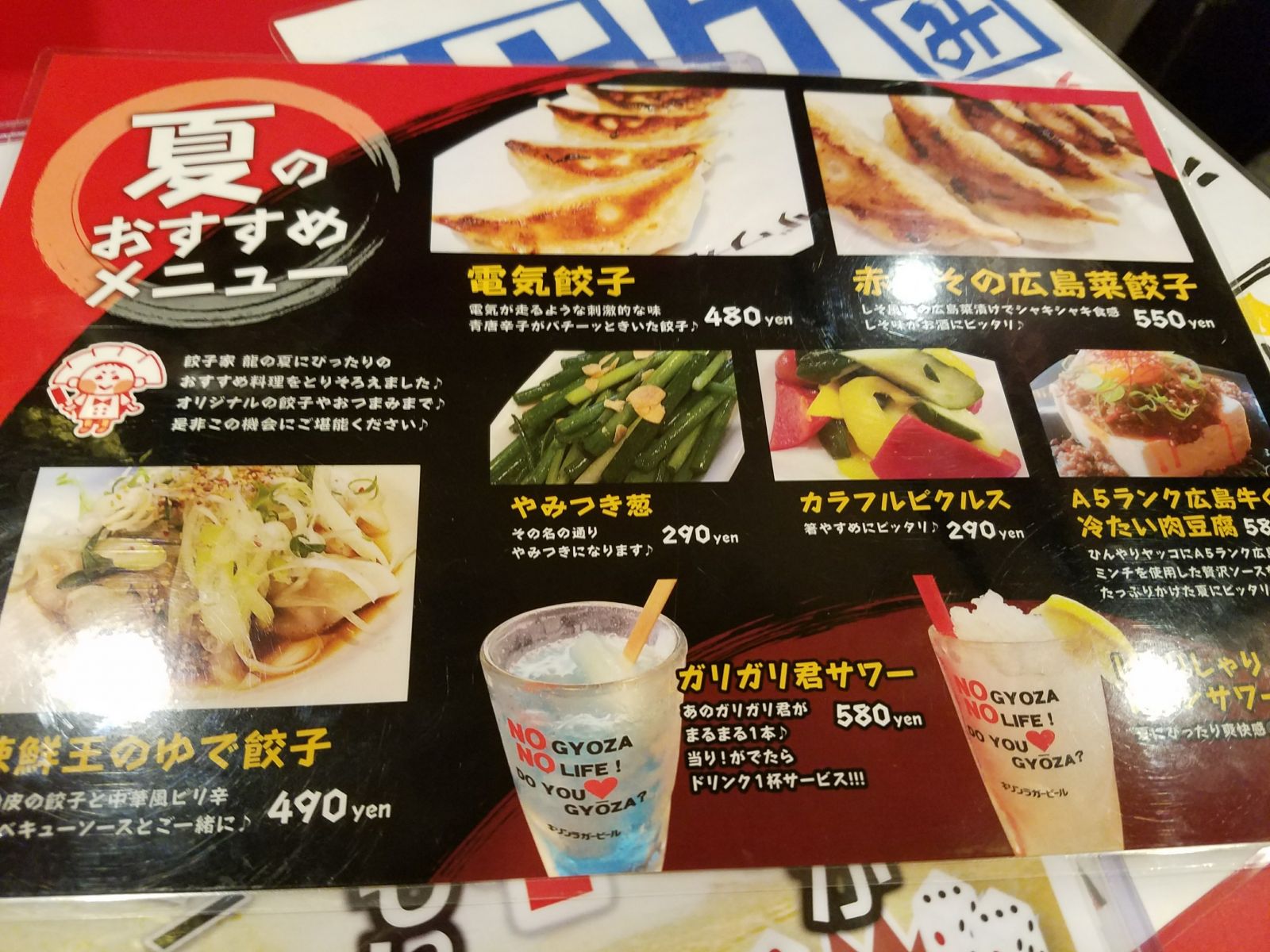インプラントの質問です。
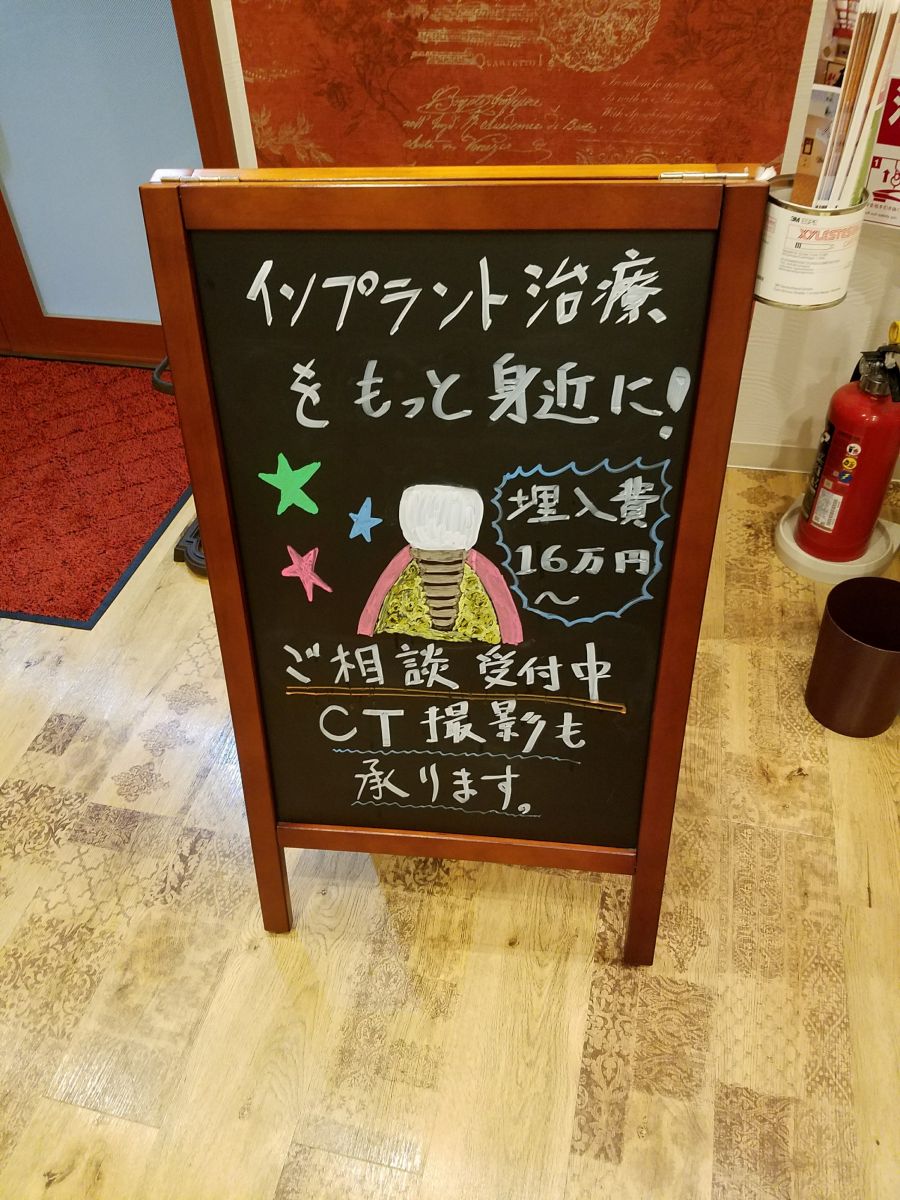
最近、細いインプラントを穴をあまり掘らずに拡げて埋めてすぐに入れられる(噛めるように)出来るインプラントがあるそうだけど、どうなんですか?と言う質問です。
先ず最初にインプラントは骨と強固に結合して機能することになりますので、細いインプラントよりは太いインプラント体の方が骨と接する表面積が大きいですのでより咬合力に耐えることが出来ます。
一般的なサイズのインプラントを埋めることが出来れば問題ないのですが、極端に細くなると強度的な面で問題になると思います。
またすぐに入れることが出来るというのは場合によりけりだと思います。
十分に骨植が堅固な場合は可能かもしれませんがリスクはあります。
インプラントを埋めたとしてもすぐに骨と結合するわけではありませんので、骨と結合するまでの期間、咬合力が加わってもインプラントが動かないという前提がありますが、人によって咬合力に差がありますし、骨を折った人がまだくっついてないけど完全に動かないように固定しているので使っても動かなければ骨はくっつくという理屈のようなものです。
理論的には可能でしょうが、かなりリスクはあるというほかありません。
失敗してもいいのならやりましょうと言うのでしょうか?
そういうわけにもいきませんから、私は即時加重はしません。
経験上不可能ではないと思いますが、少しでも失敗することが無いように、確率の高い方法にするべきかと思いおこなっていないだけです。
それはドクターの考えによっても患者のニーズによっても変わってくるでしょうから、どちらが正しいのかとは言えないと思います。
ただできる限り不確定な要素を排除したいと思って治療しています。
ですので、すべての症例で即時加重可能と言うのはちょっと違う気がしますが・・・
あと、拡大して埋めていくということですが、これは昔からある方法ですが細かく大きさを上げていってホールを作っていく方法だと思いますが、
似たような方法もいろいろ試したことはありますが、骨の硬さによって、すべてが同じように拡大できるわけでも無かったですし、やわらかいほうにズレてしまいますし、
とりあえず埋まればいいというわけでもありませんので、使うことはありますがGBRを併用したりすることが多いですので、拡大の方法だけでまったくGBRが要らないとは言えません。
それゆえ、拡大するだけで埋入できるというようなことは言えないわけです。
選択肢を狭めるようなことは当医院ではいたしておりませんので・・・
答えになりましたでしょうか・・・